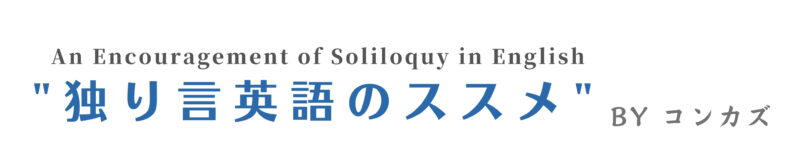どうも。コンカズ (@konkazuk) と申します。
新型コロナウイルスの影響で1年延期されたあと、COP26(国連気候変動会議)は、2021年にイギリスのスコットランド、グラスゴーで開かれました。
今回は、気候変動対策における大きな節目とされ、パリ協定で決まった内容を具体的にどう実行していくかが決められた、この「グラスゴー会議」の内容を3つの大きなポイントに絞って見ていきます。
1.5℃目標を改めて確認 – なぜ重要?

2015年のパリ協定で定められた目標は「気温上昇を1.5℃以内に抑えること」でしたが、実際のところ、COP26 (グラスゴー会議)の前には「2℃でもいいのでは?」という意見がまだまだ残っていました。
1.5℃と2℃ではかなりの大きな違いがあり、例えば2℃に達すると、赤道付近の国では作物が育てられなくなり、海抜の低い島国は海面上昇によって、国そのものが水没する危険にさらされることになります。
と言うわけで、科学者や気候活動家が強く訴えてきた「1.5℃目標を本気で守る」ことが、COP26で再確認されたのは、とても大きな意味を持ちます。
さらに、各国には2030年までに排出削減計画(NDC=Nationally Determined Contribution)を更新することが求められました。
つまり「ここ10年の間にどれだけ本気を出せるか」が問われる、2050年のネットゼロ達成に向けた短期的な目標も設定されたということになります。
石炭火力と化石燃料への言及

1.5℃未満の実現に必要な排出削減のレベルにもってくるためには、全世界の温室効果ガスの排出量の75%以上を占めている化石燃料(石炭、ガス、石油)の問題に正面から向き合わなければなりません。
このグラスゴー会議が注目された理由は、合意文書の中に初めて「石炭火力の削減」、そして「化石燃料補助金の段階的廃止」が書き込まれたことです。
過去に行われてきた国連気候変動会議の中で、ここまで踏み込んだ言及が入ったことはなかったので、環境NGOや若い世代の活動家からは「ついに化石燃料にメスが入った!」と賞賛されました。

ただし、元々は「石炭火力を廃止(phase-out)」と書かれていたのが、中国やインドなどの新興国の反対に遭い、最終的には「少しずつ減らす(phase-down)」という表現に落ち着くことになってしまいました。
しかしながら、これまで一度も合意文書に直接「化石燃料」に触れる内容がなかったので、これは大きな転換点だった言って良いでしょう。
気候被害への「損失と損害」基金の設立へ

この部分に関しては、正直なところ、メアリー・ロビンソンさんによる著書「クライメート・ジャスティス」を読んでいただきたいのですが、つまりは、
「気候変動に最も責任のない途上国の人々が、先進国の温室効果ガス出したい放題が原因で、洪水や干ばつなど、命に関わる深刻な被害を受けている。アンタらその責任を取ってくれ!」
という事です。
もっともな話なのですが、上から目線の先進国は「えっ、それって援助やチャリティの範囲でしょ」といった感じで、長い間この問題を適当にはぐらかして来ました。
でも、このグラスゴー会議では、気候変動の被害を強く受ける途上国からの強い訴えにより、「損失と損害(loss and damage)」を補償する仕組みづくりが、ついに前進。
実際にどれぐらいの金額が集まって、それがどのように使われるか?という課題は残っていますが、途上国にとって、先進国が資金を出して途上国の被害をサポートすることに合意したのは、長年の要求がやっと形となった歴史的な瞬間だったと言えます。
まとめ

というわけで、グラスゴーで開かれたCOP26は「パリ協定を動かすための中身を整えた会議」だったと言えます。
それぞれ状況が異なる国の間で物事を進めるのには、それなりの時間がかかりますし、課題もまだ山ほど残っていますが、世界が「1.5℃目標を守るために本気で動き出した節目」と言えるでしょう。
あとは各国が、その約束を守るかどうかにかかっています。
それではまた。
コンカズ
*この記事の英語ヴァージョンはこちらから
👉 Glasgow’s COP26: Paris Agreement Gets Teeth with Fossil Fuel Phase-Down & Loss and Damage