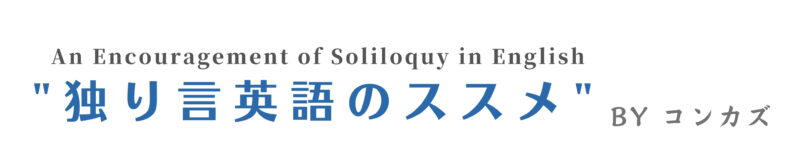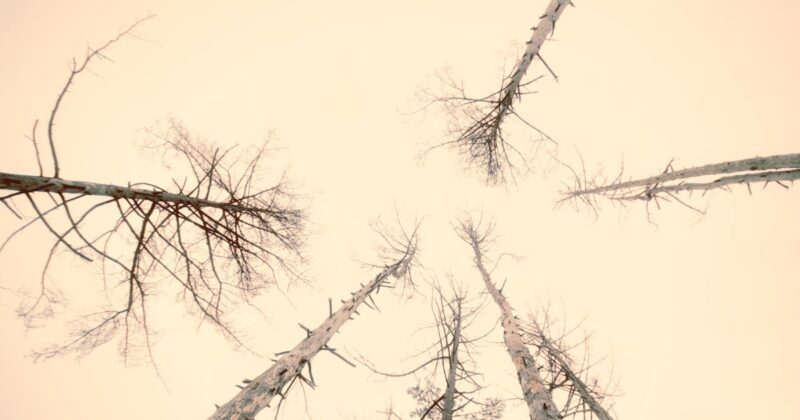どうも。コンカズ (@konkazuk) と申します。
何なんですかね。もうみんな諦めてしまっているのでしょうか?
パリ協定で産業革命以降の地球温度の上昇を1.5℃までに抑えようってことだったのに、1.7℃記録しちゃってますよ。
もうすぐ2℃到達ですよ!!!
自分が仕事中毒であるのをうまくごまかすために、「子供たちの将来のために資産を残す、もっと稼ぐぞ」なんて立派な言いわけを作って (もちろんそれも大切ですが)、現実を直視せず、よくわからない競争社会にしがみつき、気候変動にも気づかないふりを続けて…
そしてついに、よっしゃぁ〜!お金も貯めたし、家のローンも払い終わった!となったときには、世界中が食料不足、配給は滞り、難民であふれかえり、水と食料の奪い合いの生存競争が始まっている…。
「資産がたっぷりあるから、まあ何とかなるだろう」と思っていたら、スーパーの棚は空っぽ、水道も止まり、買い物どころか命の奪い合い。
なんてハッピーな将来が次の世代を待ち受けているのでしょう?
というわけで今回の記事は、2℃到達が何を意味するか?の内容となっております。
食料危機が訪れ、治安が崩壊する

「気候変動」という言葉は、すっかりありふれたものになり、「激安セール」や「1個買うと、もう1個タダ!」などの言葉と同じように、日常の中に当たり前に存在し、もはや心に響かなくなってしまっていますよね。
ということは、「熱波」「森林火災」「干ばつ」なんて言葉も当然心には響かないし、それが自分の国で起こっていない限り、どうでもいい他人事です。
いやいやいや、そんなわけありません。
他の国で起こっている出来事は、地球上のすべての国に確実に影響してきます。
まず、みんなが誤解していそうなのは、
「平均2℃上昇」というのは、地球全体をならした平均値にすぎない
ということです。
地域によっては、5℃以上の気温上昇が起こる場所もあり、特に赤道付近の国々では、すでに産業革命前より2℃を大きく超える上昇が記録されているケースも出てきています。
これじゃ、穀物が育たないです。
もうすぐそこまで来ている、世界食糧危機までの道のりを簡単に説明すると…
① まず、赤道付近の発展途上国で、猛烈な暑さ、干ばつなどによって農作物が育たなくなり、農業が崩壊する地域が次々と現れます。(ていうか、暑すぎて熱中症になってしまうので、人間自体も農作業ができなくなってしまいます。)
② 農業崩壊で、現地で深刻な食糧難が発生すると同時に、輸入に頼る国々でも、供給不足によって食料価格が世界的に高騰。
③ 食料と水を求めて、生存のために安全な場所を目指して大移動が起こります。「気候難民」と呼ばれる人々が国境を越え、世界各地で社会的不安が拡大し始めます。
④ 難民問題や政治的な緊張が、日本にとっても重要なチョークポイントであるスエズ運河やマラッカ海峡などに影響し、食料や資源を運ぶルートが滞って、さらに価格が跳ね上がります。(海賊なんかも現れそうですね。)
⑤ 物流の混乱から、食料の奪い合いが先進国でも始まり、治安が乱れます。「豊かな国にいるから安心」という幻想は崩れ、スーパーの棚から食料が消え、高騰した価格にみんなが苦しむ状態になれば、国内では空き巣や強奪、殺人などの犯罪は日常茶飯事となり、国レベルでは戦争が始まる可能性もかなり高いです。
つまり、気候変動に対して無視をキメ続けて、今まで通りの生活を続けているのは、食糧不足や戦争が始まるのを指をくわえて待っているようなものです。
もうのんびりしている暇などこれっぽっちもありません。
現在まだ食糧危機が起きていない理由

いま、地球では静かに、しかし確実に「食料危機」へのカウントダウンが始まっています。
アフリカ、中東、南アジアなどの赤道付近の国々では、干ばつや洪水、熱波による農業被害がすでに深刻化しています。作物が育たず、収穫が激減している地域も少なくありません。
それではなぜ今のところは、とりあえずバランスが取れているのか?
それは、北の高緯度の国々で、温暖化によって農業に適した土地が増えたため、収穫量が一時的に増えているからです。
実際、カナダでは小麦の生産量が伸びたり、ロシアでは新たに農地が拡大したりしています。
つまり、全体として見れば、「世界全体が一気に食糧危機に陥る」という状況にはまだなっていないのが現在です。

貧富の差が広がっても、超富裕層が大きく稼いでいるため、貧しい人の収入が減ってもGDPは維持されている… そんなイメージに近いですね。
しかし、この「北の国々のプラス効果」が、ずっと続くわけではありません。
温暖化がさらに進めば、これまでプラスにはたらいていた北の地域でも、予測不能な天候によって干ばつや洪水が起き始めます。
そうなれば、当然ながら世界全体の農業生産は一気に落ち込み、これまで隠れていた食料危機が表面化してきます。
サンゴ礁の死滅

サンゴ礁は1.5℃上昇でもかなりの打撃(最大90%死滅)を受けると言われていますが、2℃上昇になるとほぼ全滅します。
「海の熱帯雨林」とも呼ばれるサンゴ礁は、海洋生物の4分の1が繁殖地・生息地として依存しているため、これが世界から消えてしまうと、魚も姿を消します。
魚がいなくなるということは、人間が魚を食べられなくなるのはもちろんのこと、魚を食べて暮らしている海洋生物も死滅することを意味します。
これによって、地元の漁師たちは生計を失い、経済的にも大きな打撃を受けることになります。
さらに、サンゴ礁は「天然の防波堤」としても機能していて、高波や台風による波の力を吸収してくれているのですが、これがなくなると沿岸の街は、高潮や津波の被害をもろに受けることになります。
波の力が直接海岸に当たるため、砂浜が削られ、さらに温暖化による海面上昇も重なって、土地が失われるスピードが加速します。
じゃあ、どうする?

じゃあ、何ができる?ってことになりますが、僕が思うに、一番大切なのは地球のどこに住んでいようと「気候変動が深刻な問題」という現実をちゃんと受け入れて、毎日の生活の中の優先順位のトップに持ってくることだと思います。
そしてまずは、
しっかりと興味を持って、気候変動について色々と調べながら勉強していくことが重要です。
毎日が忙しいので、もちろん何もできない日もあると思いますが、それでも気候変動のことは優先順位のトップリストとしてキープしてください。
勉強を続けていくと、そのうちに知識が増えていき、事の重大さをさらに理解することができるので、家族やまわりの人たちにも「なぜこんなことが起こっているのか?」「なぜこれを解決しないとヤバいのか?」といったことが説明できるようになります。
個人レベルでは「自分にできることなんて小さい」と思いがちですが、自分が勉強し、身近な人たちに知識を広げていくことで、意識を持つ人たちの輪は少しずつ広がっていきます。
そして、それがあちこちで広がり、何百万・何千万単位で集まれば、大きな力になります。
そうしたら、同じような意識を持った人同士で連絡を取り合って、環境保護に関連したイベントに月一で参加したりなど、活動の範囲が広がっていきます。
とにかく、私たちは、自分の老後や子どもの将来、そしてその次の世代に必要とされるものを、ものすごい勢いで補充もせずに盲目的に消費していて、しかも、その消費しているものは、自分と直接関わっていない場所で作られているため、その実態が全く見えていません。
行動できるようになるためには、この「見えていない部分」を知ることがとても重要です。
最後に、ここで個人レベルでもできることの例をあげておきます。
🔹 週に何日かは「肉なし」の食事をする
現代人は肉を食べ過ぎているため、世界で収穫される大量の食料が、発展途上国の飢えている人たちの元へ届かず、家畜のエサに回されています。
ジョージ・モンビオさんの著書 “Regenesis” によると、地球上にいる哺乳類の全体の重さの内訳は、
家畜 ➡︎ 60%
人間 ➡︎ 36%
野生動物 ➡︎ 4%
かなりショッキングな数字じゃないですか?
さらに、その家畜のエサを育てる場所を確保するために、森林伐採が進んでいるという、何とも悪循環に陥っています。
したがって、ベジタリアンやビーガンになるのは無理でも、世界中の人が週に何日か「肉を食べない日」をつくるだけで、かなりの変化を起こすことが可能です!
🔹 移動手段の見直し
ちょっと近くのスーパーに行くのに車を使っていませんか?
目的地までが短距離なら、運動がてらに、車の代わりに徒歩や自転車で移動しましょう。
🔹 参加する
最終的には、ビジネスで利益を上げるためなら環境保全を無視して好き放題やる企業や団体と、戦わなければなりません。
これは個人の力だけでは到底無理ですが、少なくとも私たちには、環境対策を重視する政党や議員を選挙で支持することができます。
市民が団結すれば、自治体や企業に対して、気候変動への本気の取り組みを求めることも可能です。
というわけで、まだまだ勉強中の自分ですが、今回は「産業革命以降の地球の平均気温が2℃を超えるとどうなるか?」についての内容でした。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
それでは、また。
コンカズ
*この記事の英語ヴァージョンはこちらから
👉 What Happens If Global Warming Exceeds 2 Degrees?