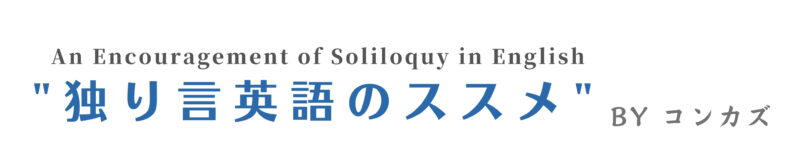どうも。コンカズ (@konkazuk) と申します。
今回は、アイルランド共和国の第7代大統領であり、国連人権高等弁務官としても活躍したメアリー・ロビンソンさんの著書 “Climate Justice(=気候正義)” を紹介します。
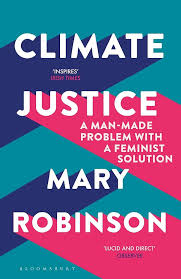
気候変動は、先進国に暮らす私たちの豊かな生活が原因で進んでいるのに、その事実に気づいていない人がまだ多くいます。
また、気づいていたとしても、便利さに慣れすぎてしまい、どこか「自分ごと」ではなくなってしまっているため、気候変動に対する危機感や責任を感じることができない状態になってしまっているのが現実です。
この本の目的は、私たちの暮らしが原因で、気候変動に最も責任のない途上国の人々が深刻な被害を受けている現実を、現地の人々の生の声を通して私たちに気づかせることです。
先進国に住むすべての人たちが読まなければならない本です。
メアリー・ロビンソンさんって何者?

まずは著者の紹介から。
メアリー・ロビンソンさんは、アイルランド共和国の第7代大統領を務めた後、国連人権高等弁務官として国際舞台で活躍した人物。
彼女は、単なる政治家や外交官にとどまらず、「人権」と「気候変動」を結びつけて語る先駆的なリーダーとして知られ、ネルソン・マンデラが設立した「The Elders」のメンバーとして国際的に活動し、今回の本のタイトルでもある「気候正義」の重要性を広め続けています。
Climate Justice (気候正義) の意味

まず、「気候正義」 とは、
先進国に比べて温室効果ガスの排出の責任がほとんどない途上国の人々が、気候変動によって命を脅かされるほどの被害を受けている。この理不尽な状況を正していこう!
という考え方です。
1850年以降に出されたCO₂のうち、アメリカとEUで50%以上を占めているのに対し、アフリカ全体はわずか数%にすぎません。
エアコンもない、車もない、電気もわずかしか使わないけど、伝統的な知恵を生かし、自然に対して「ギブ&テイク」の姿勢を貫いて慎ましく生活してきた人々が、先進国が後先を考えずに自分たちの便利のために温室効果ガスを出し続けた結果、干ばつや洪水で家や収穫を失い、命の危険にさらされています。
一方で、「テイク・テイク・テイク」で膨大な資源を消費してきた先進国に住む私たちは、堤防や保険制度といった仕組みに守られ、被害からある程度自分たちの身を守ることができる。
つまり、最も害を出していない人が最も悲惨な思いをし、最も害を出している人が守られている。
この理不尽さこそが気候正義の核心であり、ロビンソンさんが多くの人に理解してほしいと訴えている点です。
気候変動の原因を直視しようとしない私たちは、途上国の人々の生活を守ることを単なる「チャリティー」のように捉えがちですが、そうではなく、自分たちのしてきたことに責任を取る姿勢で臨まなければなりません。
具体的な現地の人たちの声

ここではとりあえず、たくさんの声の中から個人的に心に突き刺さった3人の証言を選んで、簡単にまとめてフィーチャーしています。
🔹コンスタンスさん(ウガンダ)
生活基盤が十分に整っていない地域では、女性たちは井戸へ水をくみに行ったり、畑仕事や家事に追われ、もともと休む暇がありません。ところが、気候変動によって彼女たちの生活はさらに厳しさを増しています。
例えば、ウガンダのコンスタンスさんは、こう語っています。
以前は雨が毎年同じ時期に降り、食べ物に困ることはありませんでした。だけど今は、水が少なくなり、真夜中に水くみに行って井戸で列ばなければなりません。
作物が盗まれることもあり、家庭内暴力も増え、女性たちは水や薪を求めてどんどん遠くまで行かなければなりません。
そして最終的には、干ばつや洪水で作物が全滅し、家族は飢餓の危機に直面しています。
その後、Oxfam(貧困と不正をなくすために活動する国際的なNGO)のミーティングに出席して、初めて「気候変動」という言葉を知りました。
先進国の過剰な排出が私たちの季節を狂わせていると知ったとき、とても悲しくなりました。
私たちは同じ人間であり、友人であるはずなのに、一方で彼らは快適に暮らし、私たちは干ばつや洪水で死ぬ思いをしている。
なぜこんなことをするのか、そして排出を減らしてくれるつもりがあるのかを私は知りたい。
🔹パトリシアさん(アラスカ)
地球規模での気温上昇によって氷が溶けると、露出した地面が放射を吸収し、さらに多くの氷を溶かしてしまいます。アラスカの人々は、その85%が沿岸部に住んでいて、地盤が溶け崩れていくなかで、自らの集落が目前に迫る破壊に直面しています。
自身もアラスカ先住民で、30年以上にわたり、アラスカや北極圏のコミュニティとともに気候変動の被害に対応してきたパトリシア・コクランは、こう語っています。
かつて冬は長く厳しく、夏はほんのわずかしかありませんでした。
しかし時を経るごとに、冬の訪れは遅れ、春への移行は早まり、いま私が故郷を訪れると、広大な氷原は消え去り、代わりにきらめく海が広がっています。
深刻なのは、氷の減少によって広範囲で激しい侵食や洪水が起こり、さらに永久凍土の劣化が進んでいることです。
永久凍土は、アラスカの大地を数千年にわたり支えてきた凍った地層です。
この基盤が溶けると、先住民の家々は沈み、やがて海へと倒れ込んでしまいます。
海氷が減少すれば、嵐から守ってくれていた自然の防波堤を失い、露出した土壌はむき出しとなって、海は容赦なく陸地を侵食していきます。
氷が解けることで漁や狩猟といった伝統的な暮らしは成り立たなくなり、私たちはいま「故郷を失う危機」に直面しています。
🔹アノテ・トン元大統領(キリバス)
太平洋に浮かぶキリバス共和国は、海抜わずか2メートルの小さな島々の国。
ここでは、温暖化による海面上昇によって国全体が沈む危険にさらされていて、国がまるごと消滅する可能性があるのです。
アノテ・トン元大統領はこう語っています。
私は、国際会議の場で繰り返し「このままでは私たちの国が海に沈む」と訴えてきましたが、その声は、自国の利益を優先する大国に無視される結果として終わりました。
これは、化石燃料によって経済を築いてきた先進国の指導者たちが、キリバスの死刑判決に署名したも同然です。
故郷を守れない無力感が襲い、全くやりきれない思いになりました。
もし海に沈めば、私たちは「気候難民」として他国に散り散りにならざるを得ないのです。
国を失うというのは、私たちの文化、伝統、祖先から受け継いできたアイデンティティそのものが消えると同じです。
先進国に暮らす私たちへのメッセージ

この「気候正義」を読んで確信したのは、結局のところ、たまたま地理的にラッキーな場所に生まれたり、ラッキーなことに富を握ることができた強者は、自分たちの欲を追求すればするほど、少しずつ周りが見えなくなっていくということです。
やがて周りがどうでもよくなり、自分が得るものも、まるでどこかから勝手に湧いてきたかのように手に入ってしまうため、人の苦労や痛みがわからなくなり、最終的にはすべてが他人事になってしまうのだと思いました。
例えば、あなたが先進国に住んでいて、経済的には平均より下の階層に属していたとして、社会の中で弱者として不幸を感じていても、生活基盤は整っていて、きれいな水を飲むことができます。
一方で、国外には干ばつで水不足が続き、家畜と同じ泥水を飲まざるを得ない人々がいても、自分の国のレベルでしか物事を見られないので、そうした現実を想像することはできません。
けれども、「自分さえ良ければそれでいい」という考えは通用しません。
結局のところ、私たち人類は同じひとつの惑星に住んでいるのです。
最終的に誰も逃げ切ることはできません!
気候変動によって洪水に巻き込まれたり、食糧不足で辛い思いをするのが「先にくるか後にくるか」という違いがあるだけです。
「ギブ&テイク」をやらなければ、破滅に向かうのは目に見えています。
テイクをしすぎたのであれば、ギブバックをやらなくてはいけません!
小さな一歩でも良いので、今日からアクション始めましょう。
それではまた。
コンカズ
*この記事の英語ヴァージョンはこちらから
👉 Climate Justice Explained: How the Poor Suffer While the Rich Thrive