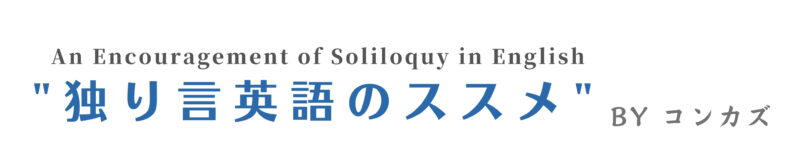どうも。コンカズ (@konkazuk) と申します。
今回紹介する書籍は、イギリス出身のジャーナリスト、環境・政治活動家で作家もあるジョージ・モンビオさんによる ‘REGENESIS‘。
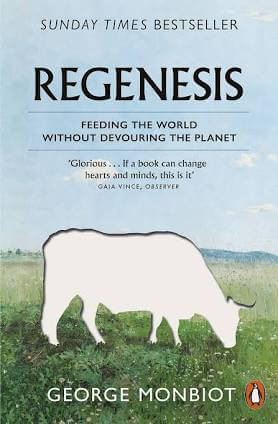
土に関する本なのですが…
「なんだ、土がどうした!俺にゃ関係ねぇ。」なんて言ってる場合じゃありません。
競争社会の中で便利な暮らしの恩恵を受ける一方で、私たちはいつの間にか自然への関心を失いつつあります。
そしてその裏側では、私たちの命に関わる深刻な事態が静かに進行しているのです。
この本では、気候変動の根本的な原因のひとつが取り上げられており、農業に携わる方だけでなく、すべての現代人に読んでほしい一冊です。
非常に多くの情報が詰まった書籍なので、この記事では、個人的に印象に残った部分をピックアップしてご紹介していきます。
ジョージ・モンビオさんって何者?

まずは著者の紹介から。
イギリスの環境活動家でありジャーナリスト、作家でもあるジョージ・モンビオさんは、イギリスの新聞 “ガーディアン” 紙で、気候変動や生物多様性の損失、資本主義と環境の関係に関する内容を長年にわたって執筆しており、彼の記事は世界中で読まれています。
主な著書には ‘THE INVISIBLE DOCTRINE‘や ‘HEAT‘ などがあり、今回紹介する ‘REGENESIS‘では、特に農業と食のあり方に焦点を当て、「持続可能な未来のためには農業そのものを根本から見直す必要がある」と主張しています。
木の根っこは内臓

この本の冒頭で、ジョージさんは、土壌や植物の根が、私たちの体にある「腸」と同じような働きをしていると説明しています。
🌲 The rhizosphere lies outside the plant, but it is as essential to its health and survival as the plant’s own tissues. It is, in effect, the plant’s external gut.
植物の根の周囲の土壌は、英語で “rhizosphere” [raɪzəsfɪr]、日本語で「根圏」と呼ばれ、ここでは植物の根から分泌される物質や、根の活動によって変化した土壌環境によって、特定のバクテリアの群集が形成されます。
そして、これらの微生物が植物に必要な栄養素を供給したり、病原菌から植物を守ったりするそうなんです。
植物の「根圏」と人間の「腸」には、どちらにも驚くほど多くのバクテリアが住んでおり、それぞれのシステムでバクテリアが有機物を分解し、植物や人間が吸収しやすい化合物に変えていることを考えると、両者が驚くほど似ていることがわかります。
個人的に印象に残った内容の一つとしては、人間の母乳に含まれている「オリゴ糖」の話。
過去に科学者たちは、赤ちゃんが消化することのできない「オリゴ糖」をなぜ母親が分泌するのか理解できなかったようなのですが、現在はその糖分の唯一の目的は、実は赤ちゃんとともに成長していく腸内細菌に栄養を与えることだったという事がわかっています。
さらには、医療で使われている多くの抗生物質 (antibiotics) も、「根圏」に住むバクテリアを使って開発されているとのこと。
つまり土壌は生きていて、バランスの取れた生態系の中で「消化」や「代謝」に近いことをしているのです。
ところが、近代農業による化学肥料や耕作によって、この繊細な仕組みが徐々に壊されてきており、かなりヤバイ状況になってきているようです。
食糧不足だって?とんでもない!

地球上では、多くの人々が飢餓に苦しんでいると言われていますが、それが本当に「食料不足」のせいなのかというと、実はそうではありません。
世界の食料生産量は、ここ半世紀以上にわたって着実に増加していて、人口増加をはるかに上回っています。
じゃあ、なんでそんなことになってしまうのか?
結論から言えば、その原因は、先進国を中心とした「肉の食べ過ぎ」によって、食料が公平に分配されていないことにあります。
まずは下に示した、現在の世界の穀物生産量の行き着く先を見てください。
⚫ 家畜の飼料用 : 約 50%
⚫ バイオ燃料用:約 10〜15%
⚫ 人間の食用:約 35〜40%
このように、世界で生産される穀物の約半分が、牛・豚・鶏といった家畜の飼料として使われているのが現実です。
ジョージさんは、本当の人口危機とは、人間の数の増加ではなく、家畜の数の増加であると述べているのですが、これはまさにその通りで、国連の予測によれば、2050年までに世界の肉の消費量は、2000年と比べて120%増加するとされているそうなんです。
こうした動物たちには餌を与えなければならない。
イギリスを含んだ豊かな国々は、自分の国で消費される肉や卵、乳製品の大部分を国内で生産していると言いますが、それは飼料を他国から輸入しているから可能になっているのです。
そして、その多くが南米からの大豆の形で輸入されていて、この大豆の生産拡大が、熱帯雨林、湿地、サバンナに壊滅的な影響を与えていると言われています。
家畜のうんこが川を殺している?

驚くべきことに、現代社会で深刻化している川の汚染問題も、実は私たち人間の「肉の食べ過ぎ」が大きな原因となっています。
ロンドン市内を少し歩くだけでも、至るところにファストフード店(特にフライドチキン)が並んでいるのが目に入りますが、その背景には、こうした膨大な量の鶏肉を供給するための、集約的な養鶏工場の存在があります。
「でも、肉の食べ過ぎが、どこでどうやって川の汚染に?」と疑問に思う方もいるかもしれません。
その疑問に対して、ジョージさんが書いていることを簡単にまとめると…
まず、鶏の餌として大量の栄養分が地域に持ち込まれる。
➡︎ ニワトリがその餌を食べ、糞として排出する。
➡︎ その糞が大量に農地に撒かれるが、土壌が栄養分を吸収しきれず、余剰分が残る。
➡︎ 雨によって、糞に含まれた余分なリン酸塩や硝酸塩が川に流れ込む。
➡︎ 川に流れ込んだ栄養分を取り込んだ藻類が、爆発的に増殖する。
➡︎ 増えすぎた藻類は、夜間に呼吸で酸素を大量に吸収するため、夜明けには水中の酸素濃度が極端に低下し、魚が窒息死する。
と言うわけで、藻類の繁殖の広がりが、養鶏場の広がりと一致しているのが理解できると思います。
特にイギリスでは「川が茶色く濁っている」のが普通になってきているとも言われていて、肉を安く大量に生産する現代のシステムが、水質汚染の大きな原因になってしまっているのです。
さらに、政府が経済を発展させるために、環境庁の人間に酪農場に対して法律を執行しないよう指示していると言うので、救いようがありません。
現代人がどうしてここまで 「肉中毒」になったのか?

現代人が「肉中毒」になっていった始まりは、まず1960年代以降の急激な人口増加と、都市への人口集中により、大量の食料供給が必要とされるようになったことにあります。
そこで、スーパーやファーストフードの普及に伴い、安価で大量の肉が消費者から強く望まれるようになりました。
すると、限られた土地や施設内で大量の家畜を効率的に飼育して、生産性を最大化しようとする「集約型畜産業(インテンシブ・ファーミング)」が登場します。
これによって肉が「高級品」から「日常的な食品」へと変わっていきました。
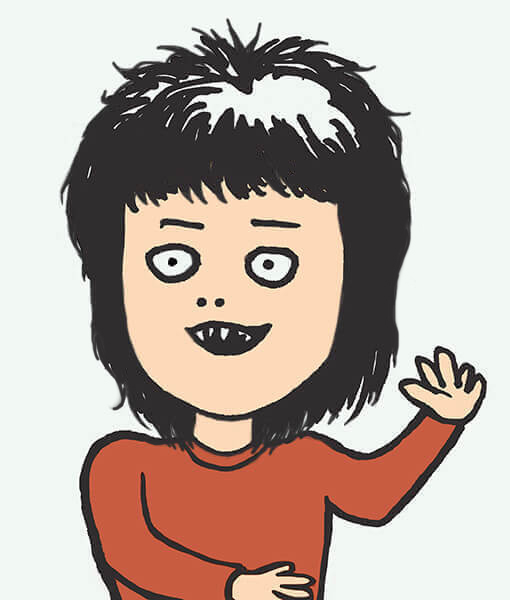
特に、マクドナルドなどのファストフードチェーンが世界中に広がったことで、手軽で安く、いつでも肉を食べられる環境が出来上がります。
さらに、加工肉やファストフードは、人間の脳が快感を覚えるように科学的に設計されているため、
食べれば食べるほど「もっと食べたい」と感じてしまい、みんな依存状態に陥ってしまうのです。
加えて、産業革命以降、ヨーロッパやアメリカの中流階級以上では「肉をたくさん食べられること」が豊かさや進歩の象徴とされてきたので、その価値観がグローバル化とともに、他の地域にも広まっていったことも、理由のひとつとして考えられます。
集約型畜産業(インテンシブ・ファーミング)の危険性

集約型畜産業では、動物たちが自然な行動をとれない高密度な環境で飼育されているので、衛生状態が悪化しやすく、ストレスによる病気も発生しやすくなります。
その結果、抗生物質が過剰に使用されることが少なくありません。
感染症の発生を防ぐために、まだ病気になっていない段階から抗生物質が投与されたり、少ない飼料で早く出荷できるよう、体重増加を促す効果のある抗生物質が使われたりしています。
一方で、土壌のバクテリアたちは常に激しい戦いを繰り広げていて、ライバルを追い払ったり破壊したりするために抗生物質を使っています。それらのバクテリアは、新たに登場する危険な化学物質にも対抗できるように、あらかじめ防御する能力を進化させてきました。
本の内容によると、家畜に投与される抗生物質のうち約58%が排泄されると推定されています。
これらの糞尿が土の中に貯蔵されると、その中にいるバクテリアは、排泄された抗生物質に耐えられるよう進化する必要に迫られます。
こうして、土壌中のバクテリアは、糞尿中のバクテリアから抗生物質への耐性を獲得していきます。
そして、このような耐性を持つバクテリア (薬剤耐性菌) やその遺伝子、さらには抗生物質そのものが、作物の根から吸収され、恐ろしいことに、私たちが食べる部分にまで取り込まれていってしまうのです。
👉 家畜に使われている抗生物質の27種類の分類のうち、20種類は人間の医療でも使われていて、その中には「最後の砦」とされる非常に貴重な薬剤も含まれています。
つまり、これが何を意味するのかと言うと…

私たちが抗生物質で治す必要がある病気にかかったとき、すでに体の中に「抗生物質が効かない菌(耐性菌)」が入ってきていると、薬が効かなくなってしまうということです!
すでにヨーロッパでは、年間2万5,000人が薬剤耐性菌による感染で死亡していると推計されていて、世界全体では何十万人もの命が奪われていると言われています。
このような理由から、科学者や医師たちは政府に対してこの危機への対応を懇願しているのですが、悲しいことに、今後15年間で、家畜に対する抗生物質の使用量はさらに3分の2増えると予測されています。💦
地球上の哺乳類の比率

今回ジョージさんがこの本の中で提示しているデータの中で、個人的にいちばん衝撃的だったのが、哺乳類の比率。
地球上の哺乳類を「体重ベース」で比較すると、現在なんと…
👉 人間が36%、家畜が60%、野生動物はたったの4% !!!
つまり、私たち人間と、食用として飼育されている動物たちが、地球上の哺乳類の大部分を占めてしまっているということになります。

もし私たちが「自然と共に生きている」なんて思っているんだとしたら、とんでもないです。実際には、自然をほとんど消費し尽くしてしまっているのです。
当然のことながら、私たちがたくさんの土地を使えば使うほど、他の生きものが住める場所や、地球のバランスを保つために必要な自然がどんどん削られていきますし、特に家畜を育てている場所では、大きな肉食動物が殺されています。
畜産が、そうした動物たちが減っている一番の理由なんです!!!
さらにショックだった内容が、EU(欧州連合)における補助金のルール。
EUでは、土地が「農業利用可能な状態」にあることが、補助金を受け取る条件となっているのですが、これは必ずしもその土地で「食料を生産している」という意味ではありません。
国によっては、実際に何も生産していなくても、土地を「農業利用可能な状態」、つまりほとんど何もない状態に保っていれば、満額の補助金を受け取ることができるのです。
つまり、「野生生物のすみか」と呼べるような再生中の森や放牧されていない湿地などが敷地内にあると、EUの主要補助制度である “Basic Payment Scheme” の対象から外れてしまいます。
そのため、補助金を受け取るために、農家たちは自然を一掃してしまうのです。
全く、気が狂っているとしか言いようがありません。
大企業による独占が「多様性」を破壊する

上で述べたような哺乳類の生物多様性の縮小は、微生物や昆虫に加え、農作物や穀物にも及んでいます。
グローバル化によってさまざまなものが世界中に届けられるようになった結果、各国の食生活が似通ってきたことにより、それを支える農業のあり方も似通うようになり、深刻な問題が起きています。
ジョージさんによると、大豆や小麦、トウモロコシなど、特定の作物だけを大量に育てる「モノカルチャー」農業では、生態系が単純化されてしまい、病気や気候変動に対して脆くなるそうです。
ある種類の作物が病気になれば、世界中で同じことが起こり、食糧危機につながってしまいますし、高速でモノが流通するグローバルな貿易ネットワークは、病原体も同じように世界中に広げてしまうのです。

世界中で同じ除草剤が使われて同じ作物が育てられていることで、除草剤に耐性を持つ “スーパー雑草” まで世界中に出現し始めているそうです。
さらに恐ろしいのは、食生活の均一化にともなって農法も画一化し、それに乗じて巨大企業がグローバル化を加速させ、小さな競合を次々に潰しているという現実。
種子・機械・農薬などの「ユニバーサル商品」を扱う大企業は、市場を支配することで政治的な力を持つようになり、その富を使って政府に働きかけ、貿易協定を自分たちに有利な形に変えていってしまうのです。
彼らは、種子や家畜品種、農薬、機械などの分野で次々と特許を取得し、企業同士の合併や買収も認可されることで、製品に対する支配力をさらに強めていきます。
現在、世界の穀物取引の約90%が、わずか4社の巨大企業によって支配されていると推定されています。💦
土は耕さない?

農業というと、まず「土を耕す」というイメージを持つ人が多いと思います。
しかし、ジョージさんのこの本では、実はその耕すという行為こそが、土壌の生命を破壊し、気候変動や生物多様性の喪失を引き起こす原因になっていると指摘されています。
耕すことで特に影響を受けるのは、次の3つ。
⚫ 土壌中のバクテリアのネットワーク
土の中には根とつながる菌糸など、大事な生き物がたくさん生息していますが、耕すとそれが壊れ、植物が栄養をうまく取れず、病気にもなりやすくなります。
⚫ 土壌の構造
土は耕すことによって一見柔らかくなるように思えますが、微生物やミミズが作った自然なすき間が壊れて、かえって土が固まりやすくなります。すると水が染み込みにくくなり、根腐れや乾燥が起きるなど、悪循環になってしまいます。
⚫ 大気中にCO₂が出る
土壌にはもともと炭素がたくさん蓄えられていて、植物の根や落ち葉、動植物の死骸が分解された有機物として存在しています。けれど、耕すことで酸素が入り込み、バクテリアが活発になって炭素をどんどん分解し、CO₂として大気中に放出されてしまいます。つまり、耕すことは温暖化を進める原因にもなります。
以上のことから、ジョージさんは、耕すことを当たり前とする農業のやり方を根本から見直し、「土壌を壊さない農業こそが、地球を修復する鍵だ」と訴えています。
土を耕さないやり方には、「ノー・ティル農法」と呼ばれるものがあり、これは土をひっくり返さずに、枯れ草や前の作物の残りで土を覆って守る方法です。さらには、トラクターで耕す代わりに、土に小さな穴をあけて種をまく専用の機械を使います。
こうすれば、土壌中の生態系を壊さずに、自然のプロセスに任せて作物を育てることができるそうです。
将来への希望

ジョージさんは、現在の農業のあり方を根本的に変えなければならないと述べていますが、その中で注目しているのが、バクテリアを使って畑や牧場を使わずにタンパク質などの栄養を作る技術。
作物が育つには何ヶ月もかかりますが、タンクの中で育てるバクテリアは、わずか3時間で倍に増えるそうです。環境さえ整っていれば、なんと1日に8回も収穫できるそうなんです。
この技術が広がれば、食料の多くを「農場なし (farmfree)」で作ることができる時代がやってきます。
バクテリアの粉は、電気さえあればどこでも作ることができるため、現在、貧しい国々での発展が期待されている再生可能エネルギーを活用できれば、大きな可能性が広がります。
ちなみに、植物由来の代替肉は、すでに動物の肉に比べて環境への負担がかなり少なく、ある研究では、温室効果ガスの排出量が鶏肉より34%、牛肉より93%も少ないという結果が出ています。

その理由はというと、大豆などを動物に食べさせて肉にするのではなく、私たちが直接食べるからです。
この技術が使われるようになれば、必要な土地は鶏肉の6割、牛肉の2%で済むことになり、水も、肥料も、農薬も、ずっと少なくて済みます。
こうやって、肉が植物タンパクに、さらに植物タンパクが微生物タンパクに置き換わっていけば、farmfree 食材の方が、安くて、質が良くて、体にもいい…という状況になります。
そして何よりも、森林伐採や牧草地拡大による環境破壊を防ぎ、家畜に頼らない持続可能な食料システムが実現できれば、森や湿地、草原などの生態系が復元され、生物多様性が回復し、自然の調和の復活へとつながるわけです。
というわけで、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
それではまた。
コンカズ
*この記事の英語ヴァージョンはこちらから
👉 Regenesis Book Summary: How George Monbiot Rethinks Agriculture and Soil