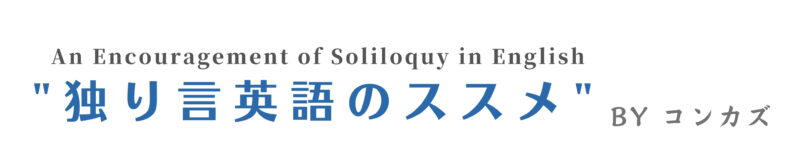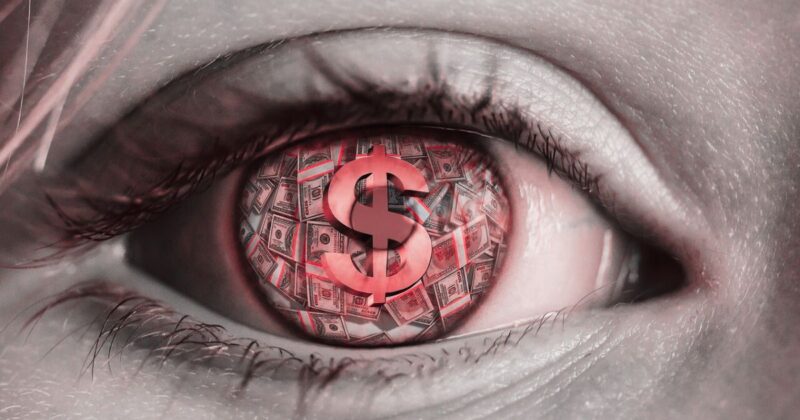どうも。コンカズ (@konkazuk) と申します。
環境ジャーナリストであり、作家としても知られるイギリスの活動家 ジョージ・モンビオ (George Monbiot) さんによるトークショーが、ハイドパーク沿いにある Royal Geographical Society で開催されたため、カミさんを連れて参加してきました。
気候変動や生態系の再生、そして政治とメディアの関係まで、鋭い視点で語られるモンビオさんの話を、直接聞けるまたとない機会です。
というわけで、今回はそのレポート記事となります。
ジョージ・モンビオさんは何者?

まず、ジョージ・モンビオさんに関してですが、彼は、イギリスはロンドン生まれの環境活動家であり、ジャーナリスト、そして作家としても広く知られていて、特に気候変動に関心をもつ若い世代の活動家たちに大きな影響を与えている人物です。
イギリスの新聞「ガーディアン」では長年にわたってコラムを執筆していて、世界中の読者から支持を得ています。
主な著書としては、“HEAT“ (日本語ヴァージョンあり)、“REGENESIS“、そして今回のトークの内容でもある “THE INVISIBLE DOCTRINE” などがあります。
TED talkやBBCにも出演しているようですが、僕が個人的にジョージさんをフォローするようになったのは、彼が YouTubeチャンネルのPolitics JOE に出演していたのを見たのがきっかけでした。👇
THE INVISIBLE DOCTRINE
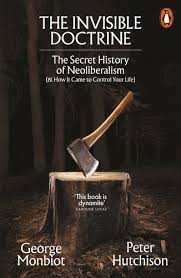
さて、今回のトークショーは、約1年前に発売されたジョージさんの書籍 “THE INVISIBLE DOCTRINE” がペーパーバック版としてペンギンブックスから発売されることになったので、そのプロモーションの一環として行われました。
前回のゲイリー・スティーブンソンさんの時と同様、How to Academy が主催するイベントでしたが、今回はゲイリーさんの時と比べて少し客層の違いを感じました。
ゲイリーさんのイベントでは、経済に関心のある比較的若い世代の男女が多く、バリバリ働いている印象の方が大多数を占めていた一方で、ジョージさんのイベントでは、少しだけ年齢層が高く、どことなく生活に余裕のありそうな方が来てたイメージですかね。
ゲイリーさんは経済の方から、ジョージさんは環境の方から世の中を少しでも良くしようと頑張っていて、その真ん中に打破しなくてはならない政治の仕組み問題が挟まっているといった感じ?

“THE INVISIBLE DOCTRINE” に関しては、10ヶ月ほど前ににオーディオブックで聴いていたので大体の内容は覚えていましたが、資本主義経済と “Neoliberalism“(新自由主義)という言葉の定義が、すごく分かりやすく説明されていた本だったと記憶しています。
結論から言うと、1980年初頭に保守党政権のサッチャー首相と、アメリカのレーガン大統領のもとで「自由経済」(規制緩和、公共施設の民営化、社会保障の削減など)へのスイッチボタンが押されました。
その結果、競争社会に参加できず取り残された人たちと、富を得た人たちとの間で格差が着々と広がっていき、もともと労働者階級を支えていたはずの労働党までもが右寄りにシフトしてしまい、現在のひどい状況につながっている、というのが大まかな流れでしょうか。
「新自由主義」の思想は、1930年代にオーストリアの経済学者たちによって提唱されて以来、富裕層やシンクタンク (ジョージさんの言葉を借りると「ジャンクタンク」)、メディア、政治家を通じて広められ、個人を「市民」ではなく「消費者」として捉える視点を社会に根付かせました。

基本のアティチュードが、テイク、テイク、テイクを繰り返して、そこが空っぽになったら次に移るというやり方なので、経済的不平等、公共サービスの劣化、環境破壊など、多くの現代的危機を悪化させてしまいます。
あとジョージさんは、新自由主義によって政治や社会の仕組みが「お金を持っている人たち」に有利になるように変えられてきたとも指摘していました。
大企業などがロビー活動をすることで政府にまで影響を与えるので、民主主義が、だんだんとお金と権力を持つ一部の人たちの影響を強く受けるようになってしまったということです。
これによって、一般市民は「自分たちの声はもう届かない」「政治は自分たちのために動いていない」と感じるようになり、そうした絶望や不満を利用して「自分が国を変える!」と主張する強い支配力を持ちたがるリーダーが現れます。
すると…
「現実的ではないけど、まだ試したことのないこの人に賭けてみようか」という心理がはたらき、最終的に、さらにイタイ目にあってしまうという流れになってしまうわけです。
まとめ

ジョージさんの話から感じたのは、競争社会、または自由経済(つまり新自由主義)は、
「もっといいところに住みたい」
「もっと旅行がしたい」
「もっといいものを身につけたい」
「子供の世代のために頑張って、もっと資産を残してあげたい」
といったように、「自分」、または「自分の家族」といった小さな単体がハッピーなったら、それがゴール達成という方向に向かってしまうので、その結果、最終的には地域のつながりやコミュニティの意識が薄れてしまうような気がします。

そして、まわりがみんなそうなので、自分だけ降りることはできません。
でも、やっぱりコミュニティーがあってこそ、「ギブ&テイク」が生まれ、人間どうしの、または環境とのバランスが取れるのだと思います。
ジョージさんは、「個人の豊かさに頼るのではなく、交通、教育、医療、自然環境など、みんなが平等に恩恵を受けられる仕組み」を強くしていくことが、政治のあるべき姿だと言っていましたが、まさにその通りだと思いました。
みなさん、そろそろ目を覚ましましょう。
それではまた。
コンカズ
*この記事の英語ヴァージョンはこちらから
👉 Neoliberalism Explained: Insights from George Monbiot’s “The Invisible Doctrine”