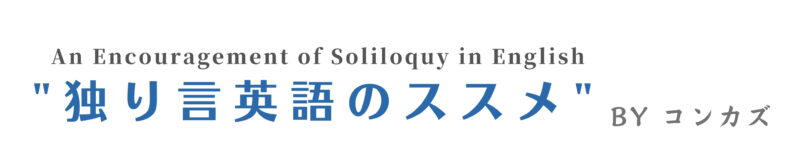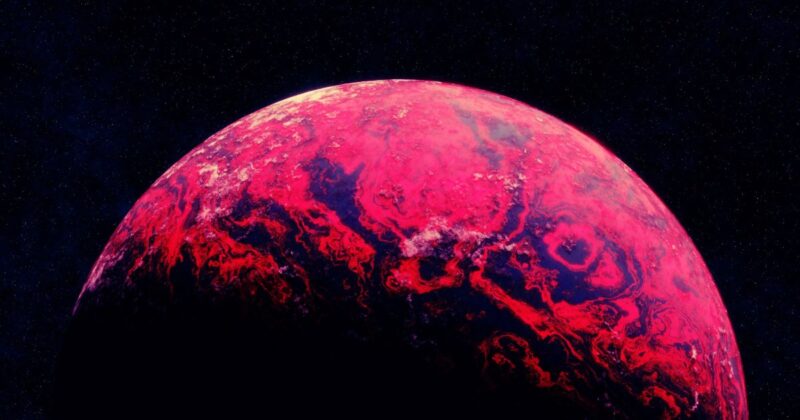どうも。コンカズ (@konkazuk) と申します。
最近インスタをスクロールしていたら、「海洋酸性化」が、ついに “Planetary Boundaries” を超え、危険なゾーンに突入した!という投稿が目に留まりました。
深刻なニュースだということはすぐに伝わってきますが、「そもそも Planetary Boundaries(惑星の限界)って何ぞや?」と疑問に思う人もいるかもしれません。
実はこの概念、ちょうど最近受講した LSE のオンラインコースにも登場していたので、ちょっとここで簡単にまとめておこうと思います。
Planetary Boundariesとは?

🔹 Planetary Boundaries の定義
まず、この “Planetary Boundaries” を日本語で表現すると、「地球環境の限界」となります。
この概念は、スウェーデンの環境科学者ヨハン・ロックストロームさんらが2009年に提唱したもので、
人類が安全に活動できる地球システムの「限界」を科学的に定義したもの。
つまり、地球のシステムがこの「限界」を超えると、大規模で急激、しかも人間の力では元に戻すことができない環境変化を引き起こす可能性があるということです。
🔹 9つの境界
地球のシステムの限界を超えない範囲で、私たちが人間社会を維持するができるように、Planetary Boundaries では、下のように「9つの境界」が設定されています。
▪️気候変動 (Climate Change)
私たちの生活から排出される温室効果ガスによって地球の気温が上昇し、異常気象が増えたり、氷河が溶けたりして、地球全体に大きな影響が出る。
▪️生物多様性の損失 (Biosphere Integrity)
多くの種類の生物が急速に絶滅していくことにより、生態系のバランスが崩れ、食物連鎖が機能しなくなり、自然が自ら回復する力を弱める。
▪️土地利用の変化 (Land-System Change)
森林伐採や都市化によって自然の土地が減少し、炭素を吸収する力や生態系の機能が低下する。
▪️淡水利用 (Freshwater Change)
川や地下水の過剰利用によって水資源が不足し、生態系や農業、さらには私たちの生活用水にも影響が出る。
▪️生物地球化学的循環 (Biogeochemical Flows)
肥料などによる窒素やリンの過剰使用が、水質汚染や湖・海の富栄養化を引き起こし、地球全体の栄養バランスを乱して生態系に悪影響を与える。
▪️新規化学物質 (Introduction of Novel Entities)
人工化学物質 (プラスチック、重金属、PFASなど)が環境中に増えることによって、地球のシステムに未知のリスクをもたらす。
▪️海洋の酸性化 (Ocean Acidification)
海がCO₂を吸収しすぎると海水が酸性化し、サンゴや貝類などのカルシウム殻を持つ生物に深刻なダメージを与える。
▪️大気中のエアロゾル負荷 (Atmospheric Aerozol Loading)
空気中の微粒子状物質(エアロゾル)が増えると、気候や降水パターンに影響が出て、人の健康にも悪影響を及ぼす。
▪️成層圏オゾン層の破壊 (Stratospheric Ozone Depletion)
フロンガスなどの化学物質がオゾン層を破壊すると、地球に届く紫外線が増加し、人間の皮膚や目、生態系にダメージを与える。
と、まぁこんな感じなのですが、これら9つのうちの1つの境界を超えると、他の境界も連鎖的に超えるリスクが高まると言われています。

僕がこの Planetary Boundaries のことを知った時点で、すでに上の表の一番上から6つの境界までが既に越えられてしまっていて、特に生物多様性、新規化学物質、窒素やリンの循環、気候変動が限界超過のレベルと知り、驚きと共に愕然としたのですが、今年さらに悪いニュースが….!!!
海洋の酸性化 (Ocean Acidification)

最近発表された報告書(Planetary Health Check 2025)によると、初めて海洋酸性化の境界が越えられてしまったと判断されています。
つまり、ギリギリ安全圏だったという段階から、危険域に入ってしまったということになります。
これにより、9つの地球の限界のうちの7つが、すでに「安全な範囲」を超えてしまったことが明らかになったのです!
分析によると、産業革命のころと比べて、海の表面のpH(海の酸性度を示す指標。数値が上がるとアルカリ性が強く、下がると酸性強くなる)が約0.1下がったとされています。
一見すると小さな変化に見えますが、実際には海が30〜40%も酸性に近づいたことになり、これは海洋生物にとってはかなり深刻なダメージです。
🔹海の酸性化と複合的な環境リスク
先ほども記述しましたが、海洋酸性化は化石燃料の燃焼で増加したCO₂が海に吸収されることで進みます。
酸性化が進むと、貝やサンゴなどカルシウムで骨格を作る生物に影響が出て、生態系や食物連鎖、そして気候調節にもリスクが生じてきます。
さらに報告書では、海洋酸性化だけでなく、土地利用の変化や淡水利用、プラスチックなどの新しい化学物質の増加、生物多様性の損失なども悪化していて、これらが互いに影響し合って、さらに悪い方向に進んでいると指摘されています。
🔹サンゴは全ての海で死滅してしまったのか?
さて、多くの海洋生物の住処として心配されている「サンゴ」ですが、世界中の海で完全に死滅してしまったわけではないようです。
僕も拝見しましたが、今年の春に公開された David Attenborough さんの映画 “Ocean with David Attenborough” では、底引き網漁などの破壊的な漁業や、海水温上昇によって引き起こされる大規模なサンゴ白化が記録されていました。
サンゴ礁を含む海洋生態系が深刻な危機にさらされているのは一目瞭然でしたが、一方で、海洋保護区において、回復の兆しが見られるという希望のメッセージもありました。

さらに、映画に伴った取り組み “Revive Our Ocean“ などが、海域保護の拡大と “No Go Zone”(人の活動を禁止する海域)の設定を促しているという情報も出ています。
つまり、サンゴは完全に「死滅」してしまったわけではないのですが、海水温の上昇や海洋の酸性化、過剰な栄養塩、藻類の異常繁殖など、根本的なストレス要因が改善されていない場所では、回復はかなり難しい状況と言われています。
そして、たとえ保護区であっても、海流や温暖化、漂流ゴミなど外部からの影響を完全に遮断することはできません。
そのため、長期的で安定した回復を目指すには、まだまだ多様な角度からの対策が必要となってきます。
最後に

以上から、現在の地球のシステムがかなり深刻な状況にあるのがわかっていただけたと思います。
どう考えても、ビジネスの拡大のために競い合ったり、自国の利益だけ考えて突っ走っていたり、またそれに気づいていても、自分一人の力ではどうにもならないと言って、何も行動しないでいる状態ではないです。
最後に、冒頭でも述べたスウェーデンの環境科学者、ヨハン・ロックストロームさんの “TEDトーク” の映像をここにフィーチャーしておくので、みなさん是非とも拝見してください。
小さな一歩でも良いので、次の世代のこともしっかりと考えて少しずつ動いていきましょう。
それではまた。
コンカズ
*この記事の英語ヴァージョンはこちらから
👉 Planetary Boundaries 2025: What the Ocean Acidification Breach Means for Our Future