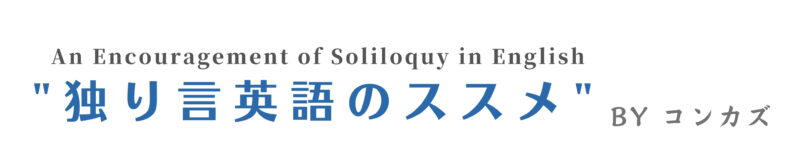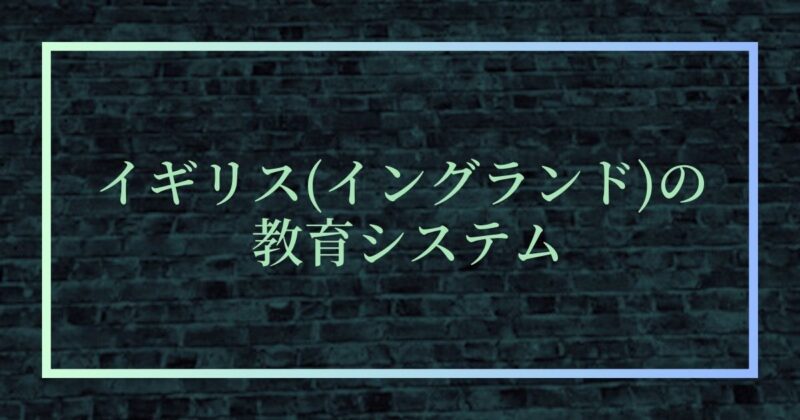こんにちは、コンカズ (@konkazuk) です。
今回の記事では、”まぁ、いつかしっかり頭に入れよう”…と思ったまま、ここまで放っておいてしまった「イギリスの教育制度」の理解を深めようと、ちょっとここらで ”パリッ” とまとめてみました。
日本の義務教育制度は、アメリカの制度を参考にしているので、小学校6年、中学校3年の、合計9年間となりますが、イギリスの場合はもう少しだけ長くなります。
何はともあれ、さっそく見ていきましょう。
義務教育を含んだ全体の流れ

まずはじめに述べておきますと、イギリスの教育制度は下の表のように、初等教育、中等教育、継続教育、そして高等教育の4つに区分されます。
| 5歳〜11歳 | Primary Education (初等教育) | Year 1 ~ Year 6 (6年間) |
| 11歳〜16歳 | Secondary Education (中等教育) | Year 7 ~ Year 11 (5年間) |
| 16歳〜18歳 | Further Education (継続教育) | Year 12 & Year 13 (2年間) |
| 18歳〜21歳/22歳 (最長28歳) | Higher Education (高等教育) | 学士課程 (3〜4年間) 大学院前期課程 (1年間) 大学院研究課程 (1〜6年間) |
*たいていの人は、学士課程まで修了すると仕事に就くため、Higher Education を終える頃の年齢は、通常21歳か22歳。
このうち、義務教育と呼ばれるものは、表のはじめの2段。つまり Primary Education と Secondary Education の合計11年間となります。
と言うわけでここからは、子供が生まれたところから、順に追っていきます。
Nursery (ナーサリー)

子供が産まれた後、まず通うことになるのが、
“Nursery” (ナーサリー)
となります。
日本でいう「保育園」にあたるわけですが、必須ではありません。
基本的には、子供が 2〜3歳、3〜4歳の「2年間」 をここで過ごすことになるのですが、子供がまだ数ヶ月、または1歳からでも受け付けているナーサリーも多々あります。
評判の良いナーサリーだと、入れてもらえるまでに ”1年以上” も待たされるところもあるので、早めに出向いて (妊娠が分かった時点でとも言われている!) 予約を入れておく(ウェイティングリストにのせてもらう) のがオススメ。
ちなみに、どのナーサリーが良いか?というのは、
Ofsted (Office for Standards in Education) オフステッド
と呼ばれる、イギリスの教育監査局ウェブサイトで調べることができます。
上ののサイトにいって、自分が住んでるエリアのポストコードを入れると、近所のナーサリーのリストとランキングが貼られているので、多少参考にはなるとは思います。
..が、やはり”ママ友グループとの交流から入ってくるナマの情報がベスト”やと思うんで、日頃からネットワーキングに励んでおきましょう。

次に、子供が義務教育に移る前に、政府から受けられる金銭的なサポートに関してですが、基本的に知られているのが次の2つ。
⚫Child Benefit
16歳未満の子供を持つ家庭で、親が所得税に基づく制限に達していない限り、全ての人が、2人目の子供の分まで受け取ることができます。(3人目からは支給されません。)
⚫15 hours Free Child Care
子供が3歳〜4歳の間、全ての家庭に週15時間 (年38週間) の無料保育が提供されます。
(共働きで、それぞれ年間最低収入の要件を満たしている場合は、週30時間 (年38週間) の無料保育。)
働きながら子供を養育している家庭を支援する目的で支給されるWorking Tax Credit や、子供を持つ親に支給される Child Tax Credit というのもありますが、これらは現在 Universal Credit に含まれます。
Reception (レセプション)

はい。そして次にナーサリーの後に子供が通うことになるのが、大抵の小学校が設けている
“Reception” (レセプション)
と呼ばれる学年。
つまり、子供が義務教育の始まりである YEAR 1 (日本でいう小学校1年生) になる前の期間。
5歳の誕生日をむかえる前までの準備期間の1年で、9月の時点で4歳の子供たちが対象となります。
実質的には、今後通うことになる学校への入学みたいなものなんで、親にとっても子供にとっても、ドキドキする行事と言えますかね。
Primary School (プライマリースクール)

そしてこの後、子供が9月の時点で満5歳になったところで、日本でいう「小学校」にあたる、
“Primary School” (プライマリースクール)
に上がります。
ここからが「義務教育」の始まりです。
学ぶ期間は、はじめに述べたように Year 1 から Year 6 までの6年間。
プライマリースクールに上がると、Key Stage (キーステージ)という言葉を耳にし始めますが、この言葉はイギリスの教育課程の基準、National Curriculum (ナショナル カリキュラム)によって分けられる義務教育の中の4つの段階を表すのに使われます。

教育制度も4つに区分されているので、はじめは頭がこんがらがります。
| Key Stage 1 | 5歳〜7歳 [ Year 1 ~ Year 2 ] |
| Key Stage 2 | 7歳〜11歳 [ Year 3 ~ Year 6 ] |
| Key Stage 3 | 11歳〜14歳 [ Year 7 ~ Year 9 ] |
| Key Stage 4 | 14歳〜16歳 [ Year 10 ~ Year 11 ] |
段階ごとに科目とその内容が振り分けられ、Key Stage 1の終わり (Year 2 / 7歳)と、 Key Stage 2 の終わり(Year 6 / 11歳)には、SATs (Standard Assessment Tests / 全国学力テスト)というテストを受けることになります。
これらのテストは、どちらかというと学校全体の学力を知るのが目的なんで、成績に関してはそこまで気にしなくて大丈夫です。
そして、ちょっとフライングしますが、Key Stage 4 (Year 11 / 16歳) では
GCSE(General Certificate of Secondary Education ・全国統一学力試験)
を受けることになります。
こちらのテストの結果は、
「進学・就職の際の合否の判断材料のひとつとなってくる」
ので、かなり重要なテストということになります。
なお、義務教育に関してですが、学校に行かずに、ホームスクーリング、(必ずしもナショナル・カリキュラムに基づいて行わなければならないというわけではない)という手段もあり、実際にこの手段をとっている親もいます。
さらに、イギリスの義務教育(Compulsory education)の期間ですが、もともとはイギリスのすべての地域 (イングランド、ウェールズ、北アイルランド、スコットランド) で5〜16歳までの11年間でしたが、
2015年から、イングランドだけ5〜18歳までの13年間に引き伸ばされています。
理由はと言うと、働くということに目を向けず、大人になっても親の元から離れられずに、コンピューターの前でブクブクと太っていく ”ニート/ NEET” (Not in Employment, Education, or Training)” と呼ばれる若者たちの増加を防ぐためと言われています。
Secondary Education (イングランド以外はここで義務教育終了)を終えたあとは…
⚫ 大学進学を希望する場合は、シックススフォームと呼ばれる学習過程 (大抵は、在籍しているセカンダリースクールに付属しているが、ない場合はシックスス・フォーム カレッジにて学習)に進む。
⚫ あるいは、農業、芸術、デザインなど、専門的な分野に進みたい場合は、継続教育カレッジ (Further Education College)、または、高等専門学校(Tertiary College) に進んで専門性の高い職業資格を得るために勉強する。
⚫ さらには、見習い・弟子 (Apprenticeships)という形で、実務経験を積みながら学ぶ。
という選択肢があります。
Secondary School (セカンダリースクール)

すでに、前回の “Key Stage” の説明で、セカンダリースクールの内容にも食い込んでしまっていますが、ここから詳しく見ていきます。
セカンダリースクールを選ぶ

プライマリースクールで6年間学んだ後は、セカンダリースクールに進むわけですが、プライマリースクールでの最後の年「Year 6」が始まって、1ヶ月ほど経つと、学校から
「セカンダリースクールへのトランスファーの申請書の書き込みの提出」
が求められます。
書き込みと言っても全てオンラインでの作業となりますが、子供に行かせたい学校を、第1希望から第6希望まで記入し、締め切り前に提出しなければなりません。
というわけで、自分の住んでいる地域に存在するセカンダリースクールの情報収集を、しっかりやる必要があります。
さらに、この時期に入ると、各学校でオープン・デーが開催されて、学校のポリシーの説明や校内の見学などが許されるので、学校の様子を自分の目で確かめたい人は、要チェックです。
ちなみに、平均レベルの年収の家庭に生まれた子供たちが通うのは、大抵の場合 Comprehensive School (俗に言われる “State school” ステイトスクール / 入学試験無し)となりますが、ここで大事なのは…
ステイトスクールは応募者のうち、学校から自宅までの距離が近い順に入学を許可する傾向にあるという事実。(キャッチメントエリアと呼ばれる。)
特に熱心な親は、子供の将来を考え、子供に通わせたい学校の「キャッチメントエリア」内に、時を見計らって引っ越すとも言われています。
というわけで、GCSEのテストがあるなど、セカンダリースクールは子供にとって将来の方向性が決まってくる重要なところなので、早くからキャッチメントエリアなどのリサーチをすることをオススメしておきます。
(ちなみに、どの学校に選ばれたか明らかになるのは、3月頃となります。)
GCSE (General Certificate of Secondary Education)

セカンダリースクールに入って4年目のYear 10(14歳・15歳)になると、2年後に控えたGCSEに向けてのコースワークと呼ばれる学習のカリキュラムに沿った勉強が始まるわけですが、その前の年の Year 9 では、すでにGCSE教科の絞り込みが始まります。
教科は選択性で、基本的には次の3つが必須科目。
🔹 English language/literature (英語)
🔹 Mathematics (数学)
🔹 *Science (理科) [生物/化学/物理]
*Sienceに関しては、生物学 (Biology)、化学 (Chemistry)、物理学 (Physics) の3つの科目を個別に勉強してテストを受ける (それぞれが、GCSEのグレード1つ分)、あるいは、3つの科目を組み合わせたもを一つのコースとして学んでテストを受ける (GCSEのグレード2つ分) “Combined Science” という選択肢があります。
続いて選択科目。
学校によって多少異なりますすが、カテゴリー別に分類されていて、その中からバランスよく何個か選ぶことになります。
⚫ Humanities (人文科学)
History(歴史)
Geography(地理)
Sociology(社会学)
Philosophy(哲学)
Religious Studies(宗教)
⚫ Languages(言語)
Spanish(スペイン語)
French(フランス語)
German(ドイツ語)
Modern Languages(日本語も含まれています!)
⚫ Arts and Design(アートとデザイン)
Textile Design(テキスタイルデザイン)
Graphic Design(グラフィックデザイン)
Three Dimensional Design(三次元デザイン)
⚫ Design and Technology(デザイン・テクノロジー)
Food and Technology(食品と技術)
Product Design(製品設計)
Textile Technology(テキスタイル・テクノロジー)
⚫ Performing Arts (表現とパフォーマンス)
Drama(演劇)
Music(音楽)
Dance(ダンス)
⚫Physical Education and Health Education(体育・健康教育)
Physical Education (体育)
必須科目と合わせて計10科目ほど選ぶことになるのですが…13歳・14歳という年齢で、大学での専攻科目を見据えて、それに必要な科目の選択を迫られるってのは、正直ちょっと大変ですね。
成績は、最終試験のExamination Paperと、Course Workと呼ばれる授業中に行われるプロジェクトの出来によって評価されますが、近年 Course Work の比重が減りつつあり、”書くことによるスキル”が試される論文形式の解答が重要視されてきているとのことです。
なお、グレード(成績)に関してですが、2017年以来 A*からGまでの旧システムに代わり、9から1までの数字が使われるようになっています。
(以前のA*とAが 現在の9から7にあたり、BとCが6から4)
詳しくは、👉 こちらから。

シックススフォームに進むのであれば、6以上が最低5科目あればセーフゾーン??? さらにいえば9または8を何個ゲットしたかが、大学を選択するのに響いてくると言う感じですかね。あーコワいコワい…
SIXTH FORM

セカンダリースクールを卒業した後、大学進学を希望する生徒は、(大抵はセカンダリースクールに附属されている)、2年間の教育課程 ’シックスス・フォーム’ に進むことになります。
’シックススフォーム’は、別名‘Key Stage 5‘ とも呼ばれ、皆さん1年目をLower Sixth (L6)、2年目をUpper Sixth (U6)と呼んでいるそうです。
もともとは、最初の年 (Year 12) の終わりに
AS(Advanced Subsidiary Level)
という試験を受け、その後の2年目 (Year 13)に
A level (Advanced Level General Certificate of Education)
の試験を受けていたようですが、2018年にイギリスの教育省が、AS試験の結果を完全にA Level のものと切り離したものすると発表して以来、AS試験は必須ではなくなり、現在のところ2年目の最終試験であるA levelを受けるだけという形になっています。
選択する科目は将来的に進学したい大学のコースに合わせて選ぶわけですが、GCSEの結果と照らし合わせながら、本人が一番楽しめる科目を選ぶのがベスト。
大抵の生徒は、初めの年で4教科を選択して、次の年で3教科に的を絞って (1教科をドロップして) 試験にのぞむと言われています。
成績は、A* A B C D E で評価され、希望大学への入学に必要な成績が取れていた場合に、入学が許可されます。
と言うわけで、
日本のように個別の入学試験はありません。
大学の学費は、現在のところ 年間10,000〜38,000ポンド (約200〜750万円 / 現在約£1=200円) と言われています。
大抵の学生は、学費と生活費のローンを国から借りて、卒業した後に一定の年収に達したら、返済していかなければなりません。
社会に出て、収入レベルをアップさせるために大学を出るのに、大学を出たら借金地獄ってどないなってんねん…?!!

ということで、みなさん最後まで読んでいただきありがとうございました。
今回の記事はここまでとなります。
僕の書いたまとめ記事が、少しでも皆さんのお役に立てたのなら嬉しいです。
コンカズ
*この記事の英語ヴァージョンはこちらから
👉 【British Education System】explained!!!
*さらに興味のある方は、こちらもどうぞ
👉 【イギリスの政治制度】をわかりやすく解説